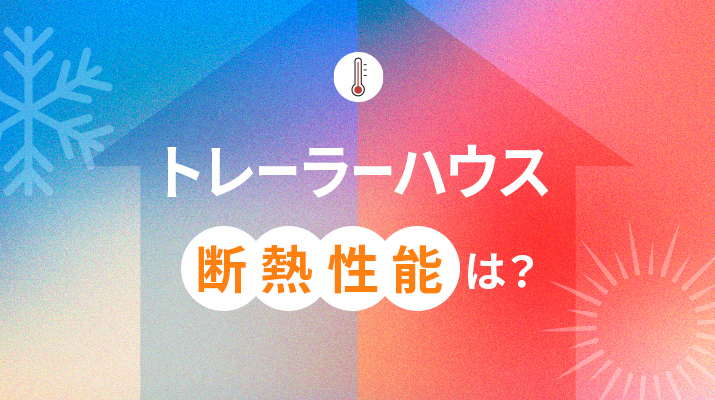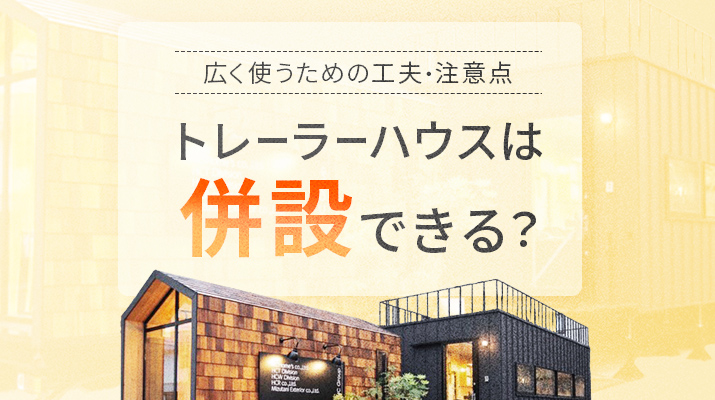コンテナハウスは後悔する?メリット・デメリットや後悔しないために知っておくべきことを解説

ー近年、おしゃれで価格も抑えられるとしてコンテナハウスが人気を集めています。しかし、安易に建てると「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。
この記事では、コンテナハウスのメリット・デメリット、購入して後悔してしまった事例などを徹底解説します。後悔しないために知っておきたい情報やコンテナハウスに関するよくある誤解なども詳しく紹介するので、購入を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
Contents
コンテナハウスの購入を後悔する主なデメリット

コンテナハウスを購入して後悔につながりやすい主なデメリットとしては、以下の4つが挙げられます。
- 想定以上に購入金額が高い
- 定期的なメンテナンスの手間がかかる
- 簡単に移動することができない
- 複雑な法律や規制に対応する必要がある
想定以上に購入金額が高い
「コンテナは安い」というイメージがありますが、住居用のコンテナはそれほど安価ではありません。輸送用コンテナは安価ですが、そのままでは住むことができないため、改修工事が必要となり、結局多額の費用が発生します。
また、住居として完成させるまでの総額は予想以上に高くなることが多いです。コンテナ本体の価格に加え、運搬費、クレーンによる設置費、建築確認申請の費用、そして法律で義務付けられている基礎工事が必須となります。
さらに、電気・水道・ガスの引き込み、内装・外装の仕上げなどを加えると、最終的には一般的な木造住宅と変わらない、あるいはそれ以上の費用がかかることも珍しくありません。初期の安価なイメージだけで資金計画を立てると、大幅な予算オーバーで後悔してしまう可能性があります。
定期的なメンテナンスの手間がかかる
鋼鉄製のコンテナハウスは、錆との戦いを避けて通ることができません。特に湿気の多い日本の気候や沿岸部では錆の進行が早く、建物の寿命を縮める大きな要因となります。
新築時には防錆塗装が施されていますが、経年劣化や飛来物による傷から塗装が剥がれると、そこから一気に錆が広がります。そのため、外壁の状態を定期的にチェックし、数年ごとに防錆塗料の再塗装を行うなどのメンテナンスが欠かせません。
防錆対策の他にも、シロアリ対策やシーリングの点検・補修なども定期的に行わなければならず、これらの手間や費用が後悔の原因になります。
簡単に移動することができない
コンテナハウスは一般的な住宅と比較して、移動できるというのが大きな特徴です。しかし、実際に移動させるのは容易ではありません。
日本の建築基準法上、住宅として認められるためには、コンテナを土地に固定する「基礎」の設置が義務付けられています。一度基礎の上に設置し、電気や水道などのライフラインを接続すると、それは法的に「建築物」となり、簡単には動かせません。
移設するには、クレーンや大型トラックを手配し、基礎から切り離して運搬し、新しい土地で再度基礎工事からやり直す必要があります。この移設には数百万円単位の多額の費用と手間がかかるため、気軽にできるものではありません。
複雑な法律や規制に対応する必要がある
コンテナを住宅として利用するには、一般の住宅と同じく建築基準法などの厳しい法律をクリアしなければなりません。特に重要なのが「建築確認申請」です。
この許可を得るためには、コンテナがJIS(日本産業規格)の認証を受けた鋼材で製造されている必要があります。しかし、安価で流通している中古の海上輸送用コンテナの多くはJIS規格に適合しておらず、そのままでは建築許可が下りません。
許可を得るために大規模な補強工事が必要になったり、そもそも建築不可と判断されたりするケースもあります。こうした法規制を知らずに購入すると、計画自体が頓挫する深刻な事態に陥ってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
コンテナハウスのメリット

コンテナハウスを購入して後悔したという人がいる一方で、コンテナハウスには以下のようなメリットもあります。
- デザインの自由度や拡張性が高い
- 耐震性や耐火性が優れている
- 工期が短い
デザインの自由度や拡張性が高い
コンテナハウス最大の魅力は、そのインダストリアルで洗練されたデザイン性と、まるでブロックを組み合わせるような自由度の高さにあります。無骨ながらもモダンな外観は、ガレージや趣味の部屋との相性も抜群です。
窓やドアの配置、内装、外装の色などを自由にカスタマイズすることで、唯一無二の個性的な空間を創造できます。コンテナを複数組み合わせたり、垂直に積み重ねたりすることで、家族構成やライフスタイルの変化に合わせて柔軟に増築できるのも大きな利点です。
将来的に部屋を追加したり、2階建てにしたりといった拡張が比較的容易なため、将来を見据えた家づくりが可能です。
耐震性や耐火性が優れている
もともと世界中の過酷な海上輸送に耐え、貨物を守るために造られたコンテナは、非常に頑丈な鉄骨構造を持っています。この構造は地震の揺れに対して優れた耐性を発揮するため、建築基準法に準拠して正しく設置すれば、非常に耐震性の高い住宅となるでしょう。
鉄でできているため、木造住宅に比べて耐火性にも優れています。素材自体の耐久性も高く、適切な防錆メンテナンスを行えば、法定耐用年数(重量鉄骨造で34年)を超えて長く使い続けることも可能です。
自然災害への備えという観点からも、コンテナハウスの堅牢性は大きな安心材料と言えます。
工期が短い
コンテナハウスは、建築工程の多くを工場で行うため、現場での作業が大幅に削減され、工期を短縮できるという大きなメリットがあります。基礎工事と並行して工場でコンテナの製造・加工を進め、完成したコンテナを現場に運び込んで設置するため、天候に左右されにくく、計画通りに工事が進みやすいのが特徴です。
一般的な住宅の工期が4ヶ月〜半年以上かかるのに対し、コンテナハウスは仕様にもよりますが最短2〜3ヶ月程度での完成も可能です。
コンテナハウスに関するよくある誤解

コンテナハウスに対するイメージはさまざまですが、中には見た目や構造のイメージから、誤解されている点もあります。主に勘違いされやすい点として挙げられるのは、下記のような内容です。
- 断熱性が低く外気温に影響されやすい
- 天井が低く窮屈になりやすい
- 雨漏りしやすい
断熱性が低く外気温に影響されやすい
コンテナハウスは外壁が鉄でできているため、熱を通しやすく外気温に影響されやすいというイメージを持たれがちです。しかし、鉄でできているのは外壁だけで、実際は一般的な住宅と同じように断熱されているので、住宅の中は適温を保つことができます。
天井が低く窮屈になりやすい
一般住宅と比較してコンパクトなコンテナハウスは、天井が低いイメージを持たれることがあります。しかし、住宅用コンテナの主流となっているハイキューブコンテナでは、コンテナ内部の高さが2.5~2.7mほどあり、これは一般的なマンションの天井高と同等かそれ以上の高さです。
雨漏りしやすい
コンテナハウスは屋根に傾斜がないため、雨が降った際に水が溜まって雨漏りしやすいといわれることがあります。しかし、住居用コンテナは雨漏りが発生しないように工場でしっかり溶接され、さらにコーキング処理も施されているため、雨漏りする心配はほとんどありません。
ただし、これは製造業者の加工技術に左右される部分でもあるので、信頼できる業者から購入することをおすすめします。
コンテナハウスで後悔しないために知っておくべきこと

コンテナハウスを購入して後悔しないためには、以下のことをしっかり理解しておきましょう。
- 基本的に輸送用コンテナには住めない
- 住宅用コンテナはそれほど安価ではない
- 建築基準法が適用される
- 固定資産税がかかる
- 移動にはそれなりの労力とコストがかかる
基本的に輸送用コンテナには住めない
安価な海上輸送用コンテナをそのまま住宅にすることは、原則としてできません。日本の建築基準法では、住宅の構造材はJIS規格適合品である必要がありますが、多くの輸送用コンテナはこの規格を満たしていないためです。
住宅として利用するには、大規模な構造補強を行い、建築確認申請の許可を得る必要があります。しかし、それには多額のコストがかかるため、住宅用コンテナを購入した方が結果的に安く済むでしょう。
住宅用コンテナはそれほど安価ではない
住宅用コンテナは、基礎工事費、断熱工事費、ライフライン接続費、内装・外装費などがかかり、シンプルな20フィート(約6畳)でも500万円ほどが費用の目安となります。家族が住める広さに拡張する場合、一般的な木造住宅と同程度の価格になることも珍しくありません。
シンプルな構造にして価格を抑えることもできますが、それと同時に住居としての快適性も失われる可能性があります。価格以外の要素も加味して、コンテナハウスを選ぶべきかを慎重に判断しましょう。
建築基準法が適用される
コンテナハウスを住居として土地に定着させる場合、建築基準法上の「建築物」とみなされます。そのため、家を建てる時と同様に、自治体への建築確認申請が義務付けられています。
申請には、耐震性や防火性などの基準を満たした設計図などの必要書類の提出が必要です。この法律を知らずに無許可で設置すると違法建築となり、行政から撤去命令を受ける可能性もあるため、必ず専門家への相談しましょう。
固定資産税がかかる
コンテナハウスは建築物として扱われるため、土地や一般的な家屋と同様に毎年固定資産税が課税されます。税額は、自治体の調査員が決定する固定資産税評価額に標準税率(1.4%)を乗じて算出されます。
評価額は、建築費用の5〜7割程度が目安です。住宅用地の特例などの軽減措置は適用されますが、維持費として継続的な税金の支払いが発生することは念頭に置いておきましょう。
移動にはそれなりの労力とコストがかかる
コンテナハウスは移動できる点が魅力でもありますが、実際は簡単に移動できるものではありません。建築確認を取得したコンテナハウスは、基礎にしっかりと固定されています。
移動するには、ライフラインの切り離し、基礎からの撤去、大型クレーンと特殊車両による運搬、移設先での再度の基礎工事と設置・接続作業が必要です。これらには数百万円単位の費用がかかるため、トレーラーハウスのように気軽な移動はできません。
代替案としてトレーラーハウスもおすすめ

コンテナハウスの代替案として、より自由度の高いトレーラーハウスも有力な選択肢です。
最大のメリットは、タイヤが付いた「車両」として扱われるため、建築基準法上の「建築物」に該当しない点です。これにより、原則として家を建てる際に必要な建築確認申請が不要となり、毎年の固定資産税がかからないという大きな経済的利点があります。
また、コンテナハウスと違って大規模な基礎工事が不要なため、設置期間が短く、コストを抑えられるのも魅力です。将来、別の場所へ移動させたり、不要になった際に売却したりすることも、コンテナハウスよりさらに容易です。
住居としてはもちろん、店舗や事務所、別荘など、場所に縛られずに空間を活用したい方にとって、その手軽さと機動性の高さは非常に大きなメリットといえるでしょう。
デメリットも考慮してコンテナハウスを購入しよう
コンテナハウスはデザイン性に富んだ魅力的な選択肢ですが、後悔しないためにはデメリットや法規制の理解が不可欠です。見た目やコンテナ本体の価格だけでなく、断熱性などの住み心地、総費用、将来のメンテナンスまでを考慮しましょう。
信頼できる専門業者と相談し、ご自身のライフスタイルと予算に本当に合うのかを慎重に見極めることが、理想のコンテナハウスライフを送るための鍵となります。
コンテナハウスの代替案として、トレーラーハウスを検討してみることも一案です。トレーラーハウスはコンテナハウスよりも自由度が高く、コンテナハウスのデメリットを克服している点も多くあります。
どちらを購入すべきか迷っているという方は、ぜひお気軽にHCTまでご相談ください。活用方法や予算などに応じて、最適なプランをご提案します。
トレーラーハウスで 見つける 新たな可能性!
トレーラーハウスについて詳しく知りたい方は
お気軽にお問い合わせください。