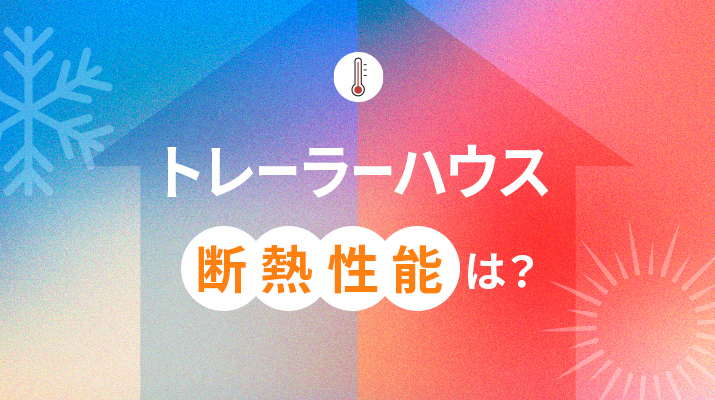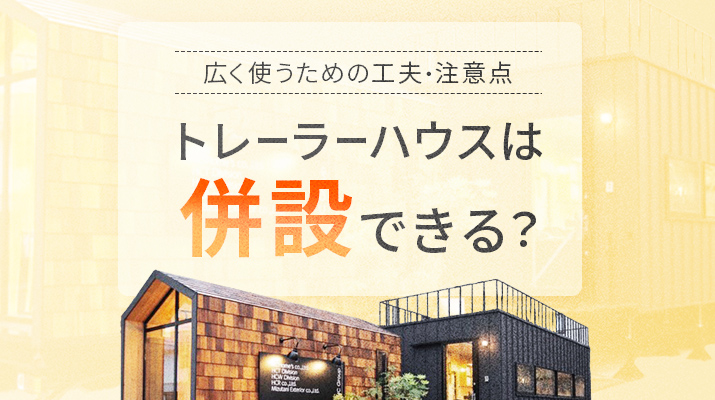ドッグラン開業の流れと成功するためのポイント!おすすめの施設タイプも紹介

ペット業界の成長とともにドッグランの人気は増加しており、近年では空地活用の一案としても注目されることが増えています。今回は、ドッグランの開業を検討している方に向けて、開業の流れと成功させるためのポイントを解説していきます。
後半では、ドッグランに必要な施設におすすめの選択肢もご紹介しているので、ぜひ最後までお読みいただき、施設づくりのヒントにしてください。
Contents
ドッグラン開業の流れ

まずは、ドッグランを開業するまでの流れを確認しておきましょう。
ターゲットとコンセプトの決定
ドッグランの開業にあたり、まずターゲットとコンセプトを決めることが重要になります。たとえば、都市部なら小型犬を中心とした少人数での利用が想定され、郊外の場合は大型犬を連れた家族層がターゲットになることが多いでしょう。
また、次のようにコンセプトをしっかり定めることで、集客がしやすくなります。
- 自然の地形を活かしたドッグラン
- 愛犬と楽しめるドッグカフェ併設
- トレーナー常駐で初心者も安心
明確な方向性を持つことで、立地の選定や設備投資の判断基準が一貫し、利用者から支持されやすい施設を目指せます。
事業計画書の作成
事業計画書では、利用料金の設定、月間利用者数の見込み、運営コストなどを明確にし、黒字化のシナリオを具体的に描くことが大切です。
たとえば、同じ地域に既存のドッグランがある場合は、価格帯やサービス内容を比較し、自分の施設の強みを明示しましょう。このほか、初期投資にかかる金額と回収期間を試算することで、投資家や金融機関への説明資料としても使えます。
事業計画書は開業後の経営指針にもなるので、定期的に見直して修正しましょう。
必要に応じた資金調達
ドッグランの開業には、土地や管理棟の整備、フェンス設置などの初期費用がかかります。そのため、自己資金で賄えない場合は、次のような方法で資金調達する必要があります。
- 銀行からの融資
- 日本政策金融公庫からの融資
- 補助金の活用
- クラウドファンディング
資金調達にあたって計画を立てる際は、余裕を持って経営できるよう、初期費用だけでなく開業後数か月間分の運転資金も入れておきましょう。
土地や建物の選定・工事
ドッグランには、犬が自由に走り回れるスペースが必要なので、立地と土地条件の選定が成功につながります。交通の便が良く、駐車場を確保できる郊外型はファミリー層に人気ですし、アクセス重視の都市型では屋内スペースを活用するケースも考えられるでしょう。
土地が決まったら、フェンスの設置や地面(天然または人工芝、ウッドチップなど)の整備を行います。事前に動線や利用シーンをイメージし、快適性と安全性を両立した空間づくりを目指しましょう。
資格や許可の取得
ドッグランの開業には、特別な資格は必要ありません。ただし、以下のような場合には形態に応じた許可や資格が必要です。
- カフェ併設:飲食店営業許可
- トリミングサロン・ペットホテル併設:第一種動物取扱業の登録
- ペットフードの製造販売・輸入:届出が必要
また、建物を併設する際には、建築基準法や都市計画法に抵触しないかの確認も欠かせません。こうした手続きを怠ると営業停止のリスクがあるため、開業準備の初期段階から調べておくことが大切です。
開業・集客
開業に向けて、オープン前からSNSやホームページで情報発信を行い、飼い主の期待感を高めておきましょう。また、無料体験やオープニングイベントの開催なども、地域の愛犬家に認知されやすくなるのでおすすめです。
集客には口コミが効果的なので、フォトスポットやSNS映えする工夫を取り入れると自然な拡散が期待できます。このほか、会員制を導入してリピート客を確保したり、しつけ教室やトリミングサロンとの連携サービスを提供したりすれば、継続的な利用にもつなげられるでしょう。
ドッグラン設計に必要な工夫

ドッグランを設計する際には、犬種や全体の安全性に配慮した工夫が求められます。こうした配慮は顧客満足度に直結するため、設計を始める前に確認しておきましょう。
犬種ごとのエリア分け
ドッグランでは、小型犬と大型犬を同じスペースで遊ばせると体格差によるトラブルが起こりやすいため、犬種や体格ごとにエリアを分けるのがおすすめです。区画を分けることで犬も飼い主も安心して利用でき、利用者満足度の向上につながります。
区画間の柵やフェンスは、視線が抜けすぎないよう設計し、犬同士に過剰な刺激を与えないようにするのも一案です。このほか、初心者用にお試しゾーンを設けるなど、しつけの程度によって分けるのもよいでしょう。
犬種に応じた設備
犬の大きさや運動能力に合わせた設備を整えることも、ドッグランづくりの大切なポイントです。たとえば、次のように
- 小型犬向け:段差の低いアジリティ器具、芝生の柔らかい地面 など
- 大型犬向け:築山、高めのジャンプ台 など
また、犬が快適に過ごせるよう、水飲み場や日陰を確保することで、季節を問わず利用してもらえます。暑さに弱い犬種のためには、ミストや浅い水遊びスペースを設けるのも効果的です。
利用者が多い時間帯でも快適に過ごせるよう、複数の休憩スペースを配置するなど、犬種ごとの行動特性を理解した設備が信頼につながります。
安全対策
ドッグランでは、安心して利用してもらえるよう、安全に配慮した設計が欠かせません。たとえば、フェンスは高さ1.5m以上を目安にし、犬が飛び越えたり穴を掘って外に出たりできない構造にします。
また、床材は犬の足腰に優しい素材を選ぶことが重要で、ウッドチップや芝生を敷くのが一般的です。さらに、場内の死角を少なくすれば飼い主が犬を見守りやすくなり、トラブルの早期発見につながります。
このほか、万が一のトラブルに備えて防犯カメラを設置するなど、さまざまな対策を検討してみるとよいでしょう。
飼い主の利便性にも配慮
犬だけでなく、飼い主も快適に過ごせるよう工夫すると、より顧客満足度を高められます。たとえば、ベンチやテーブルを設置して待ち時間を過ごしやすくする、無料Wi-Fiやコンセントを備えるなどの工夫は喜ばれます。
また、夏場には日陰や冷水機、冬場には防風スペースを用意するなど、季節ごとの対応も重要です。さらに、トイレや手洗い場、荷物を置けるロッカーを整備することで利便性が向上します。
【ドッグラン運営】成功のポイント

ドッグラン運営を成功させるためには、トラブルを防ぎ、効率的に収益を上げることが重要です。このほか、適切にコストを抑え、安定した経営を実現させましょう。
衛生管理を徹底する
ドッグランは犬が集まる場所なので、衛生管理を徹底することが信頼につながります。たとえば、排泄物は飼い主自身が処理できるよう、ゴミ箱や専用袋、水道を設置し、スタッフによる定期巡回で清潔を保ちましょう。
とくに、夏場は害虫やにおいの発生を防ぐ工夫が必要になるので、除菌消臭剤の散布や芝生・ウッドチップの定期交換が有効です。このほか、最近は感染症予防として、利用条件にワクチン接種証明の提示を求める施設も増えています。
「安全で衛生的な環境」はリピート利用を促すほか、口コミの評価にも直結します。衛生面を軽視すると悪評につながるため、日々の清掃体制をマニュアル化し、徹底して運営することが成功の基盤となります。
利用ルールを策定・明記しておく
トラブルを防ぐためには、明確な利用ルールを策定し、掲示やHPで周知することが欠かせません。たとえば、次のような利用条件を設け、基本的な安全基準を明記しましょう。
- 狂犬病・混合ワクチン接種済み
- 発情期、妊娠中の犬は利用不可
- 過剰に吠える、噛むといった癖がない
- 感染症や皮膚病に罹っていない など
また、飼い主の責任範囲も明文化しておけば、事故発生時の対応がスムーズになります。犬種や性格によっては攻撃性が出るケースもあるので、リード着用エリアや利用制限を設けるのも一案です。
こうしたルールは、利用者のためだけでなく、運営側の負担軽減にもつながります。単なる禁止事項ではなく「利用者全員が快適に使えるためのガイドライン」として明記し、利用者の理解と協力を得ることが大切です。
複数の収入源を持つ
ドッグランの運営は、利用料だけに依存すると安定性が低くなりがちです。そのため、次のように複数の収入源を設けることが成功のポイントになります。
- ドッグカフェ・物販コーナーでの追加収益
- しつけ教室の開催
- トレーニング動画の配信
- 夏季限定イベントの定期開催(プール、雪遊びなど)
こうした収益の柱を複数持つことで、利用者数の変動に左右されにくくなり、経営リスクを抑えられます。さらに、滞在時間を長くする仕組みや来場頻度を上げる工夫を意識し、売上アップを図りましょう。
近隣とのトラブルを防ぐ
ドッグランは、においや騒音などの問題で、近隣住民との摩擦が生じやすい施設です。とくに、犬の鳴き声や車の出入りによるトラブルはクレームにつながりやすいため、立地選定の段階から配慮が必要になります。
たとえば、防音フェンスや植栽による緩衝帯を設けることで騒音を軽減したり、効果的な消臭方法を検討したりしておくとよいでしょう。また、施工前に地域説明会を開き、住民に対して施設の趣旨や運営方針を説明するのも有効です。
近隣との関係は長期的な運営に欠かせないため、開業後は地域イベントに協賛するなど地域に貢献する姿勢を見せて、良好な関係を維持できるよう工夫しましょう。
ランニングコストを抑える
広い敷地や施設の維持が必要なドッグランは、運営コストがかさみやすい事業といえます。安定した経営を行うためには、ランニングコストを抑える工夫が重要です。
たとえば、地面に天然芝を使うと維持管理が大変ですが、人工芝やウッドチップであればメンテナンス頻度を減らせます。また、照明や給水設備に省エネタイプを導入し、光熱費を削減することも有効です。
このほか、管理棟やカフェとして使用する建物についても、維持費が抑えられるものを選ぶのがおすすめです。賃料や毎年の税金などは負担になりがちなので、削減できないか検討してみるとよいでしょう。
ドッグランの開業にはトレーラーハウスがおすすめ

トレーラーハウスの開業には、施設としてトレーラーハウスを用いるのがおすすめです。その理由として、主に以下の点が挙げられます。
- レイアウトが柔軟にできる
- コストを抑えられる
- 短期間で開業できる
- 競合のドッグランと差別化できる
- 不要になったら売却できる
レイアウトが柔軟にできる
トレーラーハウスは移動させられるので、ドッグランの運営スタイルに合わせて自由度の高いレイアウトが可能になります。たとえば、受付や休憩スペース、ショップ機能などを一棟ごとに分けて配置することもできるため、敷地の形状や利用者の動線に合わせて最適化しやすいのが特徴です。
必要に応じて増設や移動も容易なので、利用者数の増加やサービスの拡充にも柔軟に対応できます。事業の成長に合わせて段階的なレイアウト変更ができるため、長期的な運営において大きなメリットを発揮します。
コストを抑えられる
トレーラーハウスは、一般的な建物に比べて建設コストが低く抑えられる点が大きな魅力です。建築確認申請が不要なケースが多く、土地の状態によっては大がかりな基礎工事も不要なので、初期費用を抑えることが可能です。
また、常時移動させられる状態のトレーラーハウスは、建築物ではなく車両とみなされるので、固定資産税の課税対象にもなりません。そのため、毎年発生する税金を少なくできるのも利点です。
開業初期は資金繰りが課題になるため、比較的低コストで始められるトレーラーハウスは小規模オーナーや個人事業主にとって心強い選択肢といえるでしょう。
短期間で開業できる
建物を新たにつくる場合、設計から工事完了まで半年以上かかるケースは珍しくありません。それに対してトレーラーハウスは、製品を購入して設置するだけで利用できるため、数週間から数か月という短期間で開業が実現できます。
また、トレーラーハウスは、内装や設備もある程度完成した状態で納品されるため、追加工事の手間が少なくスピーディーに運用を始められます。事業を始めるまでのリードタイム短縮は、資金回収の早期化にもつながるので、経営面でのリスク軽減に有効です。
競合のドッグランと差別化できる
トレーラーハウスを活用することで、他のドッグランとの差別化を図ることが可能です。まだ珍しいトレーラーハウスは、外観のデザインを工夫するだけでも来場者に強い印象を与えられます。
たとえば、フォトジェニックな外観にすればSNSで拡散されやすく、集客効果を高められます。また、トレーラーハウスを複数導入して、ドッグホテル、ショップ、カフェなどの用途別に分ければ、利便性とユニークさを兼ね備えた施設になるでしょう。
とくに競合が多い地域では、こうしたデザイン性やコンセプトの違いが差別化の決め手となります。
不要になったら売却できる
事業規模の縮小や撤退を検討する際には、資産として売却できる点がトレーラーハウスの強みです。通常の建物であれば取り壊しに解体費用がかかりますが、トレーラーハウスは移動できるので、土地と分けて売却することが可能です。
中古市場も活発で、リフォームや改装をしたのちに転用するケースも多く、比較的再販しやすいのが特徴です。これにより、事業撤退時のリスクを軽減できるだけでなく、新たな投資への資金にもできる可能性があります。
柔軟な出口戦略があるのは、事業を始める上で大きな安心材料です。とくに、初めて起業する方にとっては、撤退リスクを抑えられる点が重要なポイントになるでしょう。
ドッグランを開業するならトレーラーハウスを活用しよう
ドッグランを開業するにあたり、管理棟や休憩所、カフェといった施設は顧客満足度を向上させる要素になります。ただし、一から建設するとなると開業までの期間が長くなるほか、費用も膨大になる可能性がある点には注意しなければなりません。
そこで、ドッグランの施設には、比較的容易に導入できるトレーラーハウスをおすすめします。トレーラーハウスであれば、車両として設置できるため、柔軟なレイアウトが可能になるほか、税金面の負担を軽減することもできます。
スムーズな開業を実現するため、ぜひトレーラーハウスの活用を検討してみましょう。
トレーラーハウスで 見つける 新たな可能性!
トレーラーハウスについて詳しく知りたい方は
お気軽にお問い合わせください。