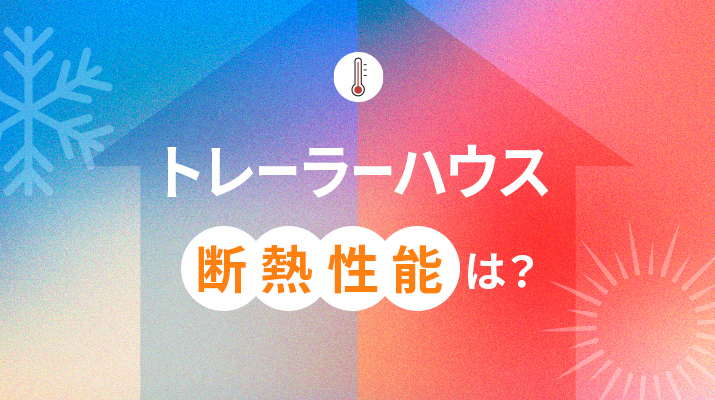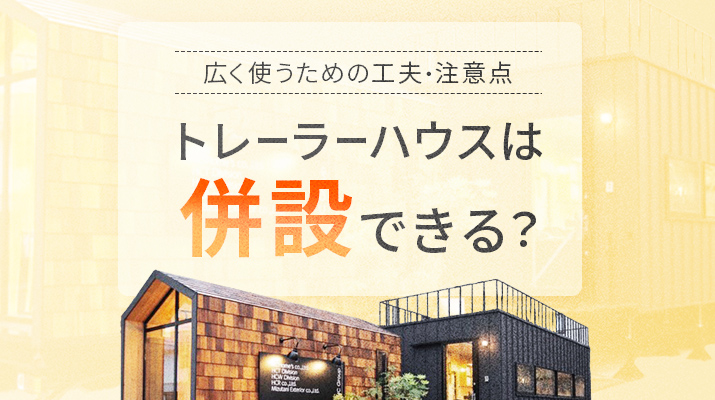プレハブの耐用年数は?気になる税金とメリットデメリットを解説

プレハブの導入にあたって、耐用年数や税金などが気になっている方は多いのではないでしょうか。
このコラムでは、プレハブの耐用年数と、導入するメリットデメリットについて解説しています。プレハブにかかる税金のほか、節税効果の高い選択肢についてもまとめているので、あわせてご覧ください。
Contents
プレハブとは

プレハブとは、「プレハブリケーション(prefabrication)」を略したもので、製造・加工を工場で行ったあと、現場で組み立てて建物を完成させる工法または建物のことを指します。日本では主に、住宅や倉庫、小屋などとして利用されており、耐久性や断熱性は製品によってさまざまです。
プレハブの種類は以下のとおりです。
- 鉄骨系:鉄骨を主要構造部に用いており、耐久性・耐震性に優れる
- 木質系:木造住宅に近い温かみのある仕上がりが特徴
- コンクリート系:鉄筋コンクリート(RC)やプレキャストコンクリート(PC)を用いた構造で、高い耐火性・耐震性・遮音性を誇る
- ユニット系:空間ユニットを工場でほぼ完成させ、現場で組み立てる
工期が短く設置も容易なため、災害時の仮設住宅やイベント用施設など、幅広く活用されています。
プレハブの耐用年数
プレハブの耐用年数は、「法的な耐用年数」と「物理的な耐用年数」に分けて考えます。
法定耐用年数
法定耐用年数とは、税務上の減価償却を行う際の基準になる年数で、建物の用途や構造に応じて定められています。
実際の寿命とは異なり、あくまで会計処理や税務処理上の基準であると理解しておきましょう。プレハブの法定耐用年数は下表のとおりです。
| 鉄骨系 | コンクリート系 | 木質系 | |
| 事務所用 | 22~38年 | 50年 | 24年 |
| 住宅用 | 19~34年 | 47年 | 22年 |
| 倉庫 | 17~31年 | 38年 | 15年 |
鉄骨系のプレハブ工法は、使用する鉄骨の厚さに応じて耐用年数が異なります。
物理的耐用年数
物理的な耐用年数は、プレハブが実際に使える年数を指します。これは、次のような要件によって差が出ます。
- 施工品質
- 材質
- 使用環境
- メンテナンスの頻度
たとえば、屋根や外壁の定期的な塗装、防錆・防水工事、シロアリ対策などを怠ると、寿命は短くなります。一方で、適切なメンテナンスを行えば、長く使い続けることが可能です。
プレハブが使える年数や資産価値を調べる場合は、不動産鑑定士や一級建築士などの専門家に依頼するとよいでしょう。
プレハブのメリット

プレハブには、一定の品質や迅速な設置が可能といったメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
品質が一定
プレハブ工法では、建物の一部またはすべてが工場で生産されるため、製品のばらつきが少なく、均一な仕上がりになります。作業環境や施工者の技術力に左右されないので、建物ごとの品質差が生じにくいのが特徴です。
また、多くがJIS規格や各種耐震基準に基づいて生産されるため、安全性の面でも信頼性が高く、建物としての耐久性やメンテナンス性に優れています。
スピーディーに設置できる
プレハブは、建材が事前に製作されているため、基礎工事後すぐに組立作業を行えるのが特徴です。一から現場で建てるケースに比べ、大幅に工期を短縮できます。
とくに仮設住宅、災害時の緊急施設では、早期の建設が人命や生活の再建に直結するため、プレハブの利点が大きく発揮されます。また、商業施設、事務所の設営などにおいては、営業開始までの期間を短縮できることによって、早期の収益化が可能です。
プレハブのデメリット
プレハブは、設置の際に建築確認申請が必要になる、原則として固定資産税の対象になるといったデメリットも存在します。手間や費用が大きくなる可能性があるため、事前にこれらの内容を把握しておきましょう。
多くの場合建築確認申請が必要
プレハブ工法の建物は、通常の建築物と同じく、建築基準法が適用されます。そのため、以下のような条件の場合には、建築確認申請が必要です。
- 建築基準法における建築物に該当
- 都市計画区域に設置
- 床面積10㎡以上
- 一定の期間設置する
建築確認が必要であるにも関わらず、申請をせずに設置してしまうと、違法建築と見なされる可能性があります。条件を知らずに設置すれば、法的手続きの壁にぶつかることがあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
原則として固定資産税の対象
建築法では、以下のような建物は建築物とされ、固定資産税の課税対象になります。
- 屋根があり3~4方向を壁で囲まれている
- 基礎など土地に固定されている
- 目的(居住、貯蔵、作業など)を果たせる状態にある
たとえば、基礎にしっかりと接地し、恒久的に設置されているプレハブ住宅や事務所などは、通常の建物同様、毎年の固定資産税が課せられます。また、仮設であれば税金はかからないと誤解されがちですが、仮設であっても移動や撤去が困難な構造の場合、課税対象になる可能性が高いです。
プレハブの設置では、税負担によってランニングコストの増加につながるケースも考慮しておきましょう。
プレハブの代わりにはトレーラーハウスがおすすめ

プレハブの変わりには、設置しやすく節税効果も期待できるトレーラーハウスがおすすめです。ここでは、トレーラーハウスのおすすめポイントを5つ紹介します。
おすすめポイント①建築確認申請が不要
トレーラーハウスを車両として設置すれば、建築確認申請は不要です。ナンバープレートを取得し、いつでも移動できる状態で設置しましょう。
設置のために基礎工事をする必要がないので、手続きの簡素化とあわせ、よりスムーズに導入できる点が魅力です。
ただし、土地やデッキなどに固定されている、ライフラインの着脱が工具なしで簡単に行えないといった場合は、建築物と見なされるため注意が必要です。また、自治体によっても基準が異なるので、事前に確認しておきましょう。
おすすめポイント②設置場所の自由度が高い
前述のとおり、トレーラーハウスは車両として扱われるため、設置場所に関する法的制限がプレハブより少ないのが特長です。市街化調整区域など、プレハブの設置が原則的に禁止されている地域でも、車両であれば置くことができます。
また、移動が前提の設置方法になっているため、不要になった際の撤去や移設も容易で、資産としての柔軟な活用も可能です。
おすすめポイント③居住性が高い
近年のトレーラーハウスは、見た目はコンパクトでも内部の居住性が非常に高くなっています。優れた断熱性のほか、空調設備、水回りなどを充実させたモデルも多く、一般的な住宅と変わらない快適さを実現できます。
また、カスタマイズ性が高いため、住居としてだけでなく、店舗、オフィス、宿泊施設など、幅広い活用が可能です。
おすすめポイント④節税効果が高い
トレーラーハウスは、設置要件を満たすことで車両扱いになるため、固定資産税や不動産取得税の課税対象になりません。ナンバープレートの交付が受けられるサイズのトレーラーハウスは、自動車税や重量税自動車税を支払う必要がありますが、不動産にかかる税金と比べて負担は小さく済みます。
これにより、結果として長期的な維持コストを、プレハブよりも低く抑えられる可能性があります。また、事業用途で使用する場合は、減価償却期間が車と同じ4年である点もメリットです。
ただし、実際に車両扱いと認められるためには、移動できる構造や、ライフラインの接続方法などに一定の条件があります。そのため、税務上の取り扱いについては、専門家と事前に相談するのが望ましいです。
プレハブとトレーラーハウスを比較してみよう
プレハブは、スムーズに導入できる点で優れていますが、原則として固定資産税や建築確認の対象になります。一方で、トレーラーハウスは車両として設置できるため、建築法の制限を受けず、不動産にかかる税金の対象になりません。
また、車両扱いであるために減価償却期間も4年と短く、集中的に節税に取り組むことが可能です。このように、トレーラーハウスとプレハブは、税負担の面で大きく異なる可能性があるため、事前にしっかりと比較したうえで選択する必要があります。
トレーラーハウスで 見つける 新たな可能性!
トレーラーハウスについて詳しく知りたい方は
お気軽にお問い合わせください。